 |
ホオジロ |
| ホオジロの雄は、木の先や電線などの目立つ場所で、胸を張ってさえずります。雌は雄よりも少し地味な体色で、行動もあまり目立ちません。 |
野鳥の楽園では、大井川に飛来する野鳥を紹介していきます。
(写真は野鳥の壁画を写したものです)
|
春〜夏 |
| ヒバリ |
| 空高く舞い上がってさえずるヒバリは、人々によく知られています地面に降りて鳴くこともあります。 |
 |
ホオジロ |
| ホオジロの雄は、木の先や電線などの目立つ場所で、胸を張ってさえずります。雌は雄よりも少し地味な体色で、行動もあまり目立ちません。 |
| キアシシギ |
| 春と秋に普通に見られるシギです。全長25cm位。体は灰色で、黄色い足。ほかには、あまり特徴のない鳥です。『ピューイ』と鳴きます。 |
| キョウジョシギ |
| 春と秋に見られます。ちょっと変った模様の鳥。波打ち際で餌をとっていることがあります。飛んだ時の背中の模様が特徴です。 |
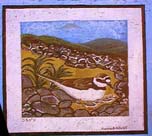 |
コチドリ |
| 河原や海岸にすむ、小型のチドリです。大井川河口周辺では、水をぬいた養魚池にもよく現われます。 5、6月に、ピュイ、ピュイ、ピュイと澄んだ声で鳴きながら、河原の上空を行ったりきたり、大きな円を描くように飛びます。こんな時は、近くに巣があるか、ヒナがいるかもしれません。 河原や荒地の砂利の間に、わずかな小枯などを敷いて粗末な巣をつくります。卵は小石にそっくりの模様で、外敵に見つかりにくくなっています。ヒナも河原の色そっくりです。卵からかえると数時間で歩き出し、工サもついばみます。親鳥は2羽で交代にヒナをあたためたり、外敵から守ったり、懸命に育てます。 明るく聞こえる、ピッピッピッピッ、ピュイ、ピュイという声が実は外敵を追い払ったり、ヒナに注意を与える真剣な叫びなのですね。 |
| セッカ |
| あまりなじみのない鳥かも知れませんが、どこの河原でもだいたい見られる普通の種類です。大きさはメジロくらいの、かわいい鳥です。 この鳥の特徴は、ヒッヒッヒッヒッ、ジャッジャッ、ジャッジャッ、という鳴き声と、鳴きながらの飛び方です。 大井川河ロでは、両岸の堤防に沿った、ススキやチカヤの草原で繁殖します。 雄は、なわばりを守るのに−生懸命で、子育てはすべて雌が行なうそうです。 |
 |
カルガモ |
| 日本で見られるカモは、そのほとんどが冬鳥として飛来するもので、日本で繁殖するのは、ほんの一部の種類だけです。県下では、このカルガモだけが繁殖しています。 体は茶色の地味な色ですが、くちばしの先の黄色と足のオレンジ色が目立ちます。カモの仲間では珍しく、雌雄同じ体色をしています。 冬には、越冬のために飛来するものが、多数あります。 |
 |
ハクセキレイ |
| 水辺だけでなく、町の中でも見られる身近な鳥です。体形はキセキレイに似ていますが、体は下面が白く、上面が黒で、白い顔に目を通る黒い線があります。 冬から春にかけて見られる鳥です。 |
|
秋 |
| アオアシシギ 全長 約35cm |
| チョーチョーチョーまたはピョンピョンピョーと鳴く。 |
| チョシャクシギ 全長 約41cm。 |
| 下に曲がった長いくちばしが特徴。ホィピピピピと鳴く。 |
| アジサシ 全長 約36cm |
| コアジサシに似ているが、一回り大型。 ギューイ、ギューイと鳴く。 大井川河口では、夏の間も少数見られる。 |
|
冬 |
 |
アオサギ |
| サギ類の中ではもっとも大きなサギです。(普通に見られるコサギは、体長約60cm。アオサギは約1m。)首をちぢめ、ゆっくりとした羽ばたきで飛ぶ姿は雄大で、ツルと見間違えるほどです。 大井川河口では、7月頃から3月頃まで見られます。川や近くの養魚池で魚をとっているのを時々見ることがあります。大井川の中洲の砂利の上で、昼間、100羽程度の群が、首をちぢめ片足で長時間休んでいます。人が近づいたりすると、警戒して一斉に飛び立ってしまいますが、その光景は壮観です。 大井川河□で見られるものは、越冬のために飛来したもので、ここでは繁殖しません。県内では昭和58年春、静岡市日の本平物園の敷地内に巣をかけた2羽が、ヒナを育てているのが確認され、初めての記録となりました。 繁殖する時には、高い木の上に集団で巣をつくります。 |
| セグロカモメ |
| 全長約60cm。大型のカモメの仲間。背、翼は灰色で、翼の先端が黒く、体のほかの部分は白。くちばしは黄色で、先端の下の部分に赤い斑がある。足はピンク。 日本には冬期越冬のため、シベリアなどから多数渡ってきます。県内では、大井川などの大きな川の河□や港などでよく見られます。カモメの仲間では、ほかにユリカモメ、オオセグロカモメ、ウミネコ、カモメなどがいますが、大井川ではこのセグロカモメが一番多く、その数1,000羽近くを数えることもあります。中洲などで、数百羽の群れで休んでいる姿をよく見かけますが、時々一斉に飛び立ち、群舞を見せてくれたり、上昇気流にのって輪をえがきながら高く舞い上がったりします。 付近の養魚池や港で、魚をねらっていることもよくあります。エサは生きた魚だけでなく、残飯なども食べます。 群れに混っている、同じ大きさの黒っぽい鳥は幼鳥です。 |
 |
ウミネコ |
| 背は濃い灰色で、尾の先に黒帯がある。くちばしは黄色で、先端に赤と赤黒の斑。足も黄色。大きさはセグロカモメとユリカモの中間くらい。冬鳥ですが、夏でも若鳥が見られます。 |
 |
ユリカモメ |
| 秋から春先にかけて、付近の港や河原で普通に見られる。カラスよりも少し小さなカモメ。足とくちばしが赤く、つばさは銀白色に輝いて見えます。 |
| キンクロハジロ |
| コガモより少し大きく、雄雌とも冠羽がある。雄は、腹からわきにかけて白く、他は黒い。白黒のコントラストがよく目立つ。 |
 |
ウミアイサ |
| マガモとほぼ同大。雄の頭は黒緑色で、長い冠羽があり、くちばしは赤くて長い。潜水が得意で魚をとる。 |
 |
ホシバジロ |
| キンクロハジロより少し大きい。雄は、灰色の体に頭、黒い胸で分かりやすい。 |
 |
ウミウ、カワウ |
| ウは全身黒で、よく水に潜るのでわかりやすい。しかしウミウとカワウを見分けるのは、近くでないとむずかしい。大井川河口では両方とも観察される。 |
 |
マガモ |
| 体が灰褐色の大型のカモ。白い首輪があり、黄緑色のくちばし。雄は頭が緑色に光り雌はオレンジ色のくちばしと白い尾が特徴 |
 |
コガモ |
| カモの中では一番小さく雄はくり色と緑の頭、体の側面に水平の白い線があり、体は灰色。 |
 |
オナガガモ |
| マガモより少し小さい。雄はチョコレート色の頭、白い胸、尾は長くとがっているスマートなカモ。 |
| ヒドリガモ |
| オオガガモより少し小さい。雄の頭は茶褐色で、ひたいは黄白色。体は灰色で、くちばしは青鉛色。 |
 |
ハシビロガモ |
| マガモより小さい。雄雌ともくちばしが平たく、体の割に大きい。雄は、黒緑色の頭、胸は白く、脇腹はくり色。 |
|
一年中見られる鳥 |
 |
コサギ 全長 約60cm |
| 純白の体に黒いくちばし、黒い足、黄色い足指が特徴。 |
 |
トビ |
| トンビのことをいう。タカの仲間では大きい方。翼を広げると150cm以上になる。大井川河口では、多く見られる。 |